
ども!SANFest会長こと『おもち』です!
心技体をMAX10段階として、基本平均以上のできれば8ぐらいを目指しているおもちです。
国語とか算数とか全然できないけど、
理科だけ毎回ほぼ満点とるようなそんな人学生時代いませんでした?
ひとつに秀でてる才能よりもとりあえず平均以上を目指せばまぁなんとかなるかなと
思いつつ今回は現物取引の『平均取得単価』について
徒然なるままに書き散らしていこうと思います。
平均取得単価とは
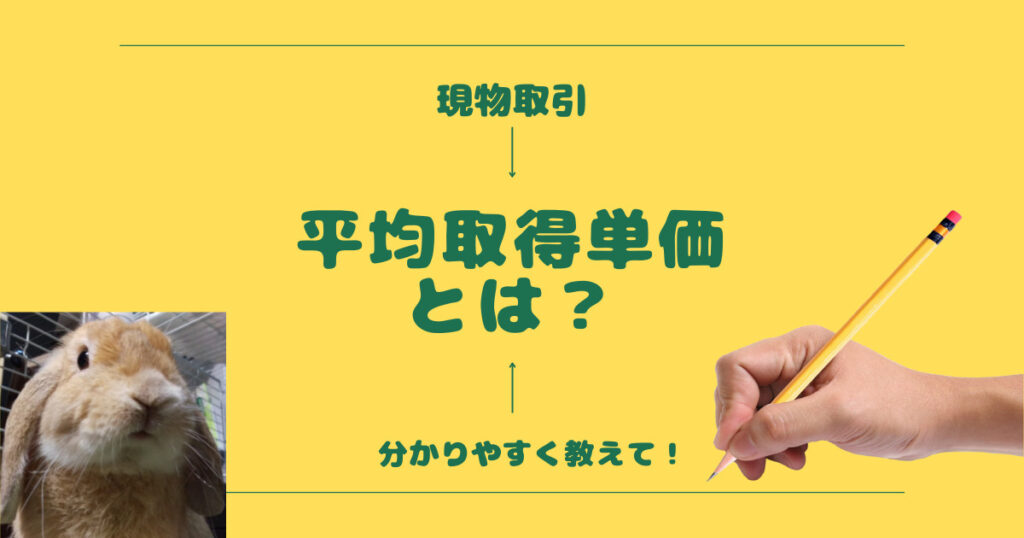

平均取得単価ってネットで検索すると色々でてきて各証券会社さんが書いてくれているけど、
どのサイトを読んでみても
「なんとなくは分かるけど、完全に分かった気にはならない」ってのがおもちの正直な感想でした。
なのでこのおもちブログでは、割と分かりやすく説明できればと思います。
あんまり変わらなかった場合はただただ平謝りです!!
ちなみに平均取得単価を知らずに株を購入した場合、思わぬ損失につながりかねないので注意していきましょう(経験あり)!
まず株における平均取得単価とは、『株を買って売るまでの代金を手数料を含めて平均した1株あたりの値段』です。
証券会社やネット証券などで株を購入する際、それぞれ条件により手数料が発生したりしなかったりします。
例えば、おもち証券で日本株を購入する際、10万円以上の売買に対しては手数料が100円かかるとします。
そして1株1000円のA株を100株買うとします。すると、
1000円×100株=10万円ですが、10万円以上の売買なので手数料が100円プラスされますので10万100円で、A株を100株購入できたことになります。
平均取得単価とは手数料を含めた1株あたりの値段なので、
10万100円÷100株=1001円なので、1株あたり1001円で購入したことになります。なので、1000円で売却するとこの地点で1円×100株=100円のマイナスとなります。売却時にも100円かかるとすると、
±0円で売却するにはA株が1002円で売却できないといけないということになります。
まずは、これが基本となります。

手数料考慮すると余計ややこしくなるなぁ。手数料全部0円にしてくれたらいいのに。。。
まぁ、平均取得単価の入り口は分かった。でももっと深く知りたい!
と、手数料を考慮するとややこしくなるのでここからは手数料なしで色々なパターンを説明します。
本来購入するときは各々証券会社などで売買手数料がつくのでそこは計算で自分でよろしくお願いします。
平均取得単価:例①追加購入
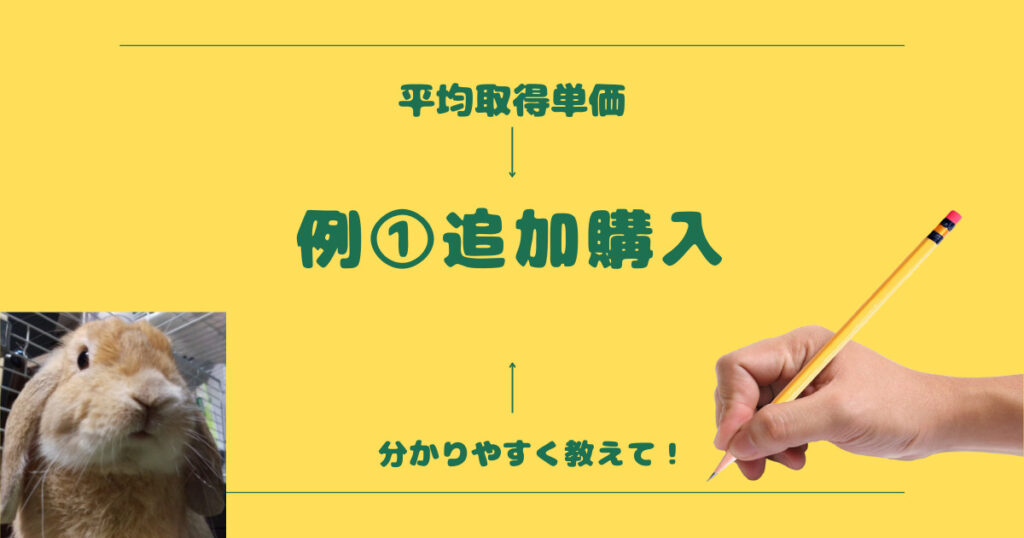
例えば、1株1000円のA株を100株購入したとします。保有したまま翌日株価が1200円に上昇しました。また上がりそうなので、追加で1200円の時に400株購入したとします。この場合、
1000円×100株=10万円と翌日1200円×400株=48万円となり、保有しているA株は10万円+48万円=58万円となり、
一株あたりの平均取得単価は58万円÷500株=1160円となり、一株あたりの平均取得単価は1160円となります。
株の超初心者あるあるで、自分は同じ銘柄A株だけど、1000円を100株、1200円を400株保有していて1000円100株は1500円になったら売って、1200円の400株は1800円で売るねん!!みたいな『同じ銘柄なのに別として売却できると思ってる説』は残念ながら違います。。合算されて平均されますのでご注意を!超初心者というかおもちが株はじめたての時にびっくりしたパターンでした。
平均取得単価:例②追加購入&売却

例えば、1株1000円のA株を100株購入したとします。翌日株価が1200円に上昇し追加で1200円の時に400株購入し、
1300円になったので500株全て売却しました。この場合、例①同様
保有しているA株は10万円+48万円=58万円となり、一株あたりの平均取得単価は58万円÷500株=1160円なので、一株あたりの平均取得単価は1160円となります。1300円で500株全て売却したので、
1300円-1160円=140円の500株なので、140円×500株=70,000円なので7万円の利益になります。
では同じ条件(1300円時)で300株だけ売却し200株は保有したままとします。この場合も、
平均取得単価は1160円で500株保有で、1300円ー1160円=140円の300株なので140円×300株=42,000円の利益で残りは平均取得単価1160円で200株を保有となります。翌日に株価が1500円になり残り200株も売却したとすると、
1500円-1160円=340円×200株なので、340円×200株=68,000円の利益となり、全部で42,000円+68,000円なのでなんと11万円の利益となりました。途中で一部売却しても平均取得価格はそのままということが分かります。
ここまでは大丈夫でしょうか?分からない人は何度か読み返してください。次からややこしくなってきます。頑張りましょう!
平均取得単価:例③売却からの当日追加購入


ここから少し難易度が上がります。難易度上がりますが非常に大事になってきます。
もちろん、おもちもはじめ何も知らずに売買して平均取得単価に気づき苦しめられたこそ、
みんなにはそうならないようになって欲しいので書き散らします。
それぐらい知っとけよ&それぐらい知ってるわって人も広い心でよろしくお願いします。
例えば以前から1株1000円のA株を100株保有してたとします。翌日株価が1200円に上昇したので100株売却しました。
しかし売却した当日さらに株価は上昇し、まだ上昇すると思ったので1400円の時に同じA株を200株購入したとします。
この場合どうなるでしょうか?見ていきましょう。
普通は1000円100株を1200円で100株売却なので、一株あたり200円の利益なので200円×100株=20,000円の利益です。
そして1400円で200株購入したので、1400円×200株=28万円で平均取得単価は、もちろん一株あたり1400円となります
と思うでしょ!!!?これが落とし穴というか平均取得単価のおもち的トラップだったのです!!!
この平均取得単価ですが、『一日の取引が終了した段階で計算を行う』ってルールがあり、どういうことかというと、同じ銘柄の株式等を2回以上に購入した場合は、「総平均法に準ずる方法」で計算します。。。これもよく分かりにくいので例としてあげると、
↑の場合、同じ日に一度1000円100株を1200円で100株売却しており、同じ日に1400円で200株追加購入しているので、この地点で平均取得単価が変動しているのです。分かりやすくすると、
1000円で100株保有していて、1400円で200株追加購入したので当日としては、
1000円で100株と1400円で200株を保有しているものの平均として計算されてしまいます。つまり、
(1000円×100株)+(1400株×200株)÷300株=1266.6666円(1円未満切り上げ)と1267円が一株当たりの平均取得単価となってしまうのです。
つまり1000円を1200円で100株売却したつもりが、1267円を1200円で100株売却したことになってしまうのです。
なんてこった!この場合、20,000円の利益だったのが、-6,700円の損失になってしまいます。では、みんなで叫びましょう!なんてこったぁぁぁぁぁ!ハリーポッターァァァ・・・落ち着きましたか?
そして残り1267円を200株保有していることになります。もちろん1400円で200株を売却した場合は、
1400円ー1267円=133円を200株なので133円×200株=26,600円の利益となり、さきほどの損失と合わせると、
26600円-6700円=19,900円の利益となりますが、平均取得単価の1円未満切り上げが発動し本来より100円マイナスになっています。
と、このように同じ日に同じ銘柄を購入する場合は現物取引の場合は平均取得単価というものに気をつける必要があります。ちなみに信用取引の場合は取得単価の計算ではなく単価ごとで取引になります。
このややこしい計算に加えさらに手数料が加算されたりするので余計ややこしくなってしまうのですが、大体こんな感じになります。
違う銘柄を購入する場合はもちろん平均されないのでややこしいのを避けたい場合は、当日に現物取引で何度も取引しないか、
取引する場合は1銘柄につき1日1度の売買などとした方が初心者は分かりやすいかもです。慣れてきたら全然OKです!
ではどんなときに平均取得単価を利用したらいいでしょうか?メリットデメリットありますが、次に見ていきます。
ナンピン買い(難平買い)を利用する
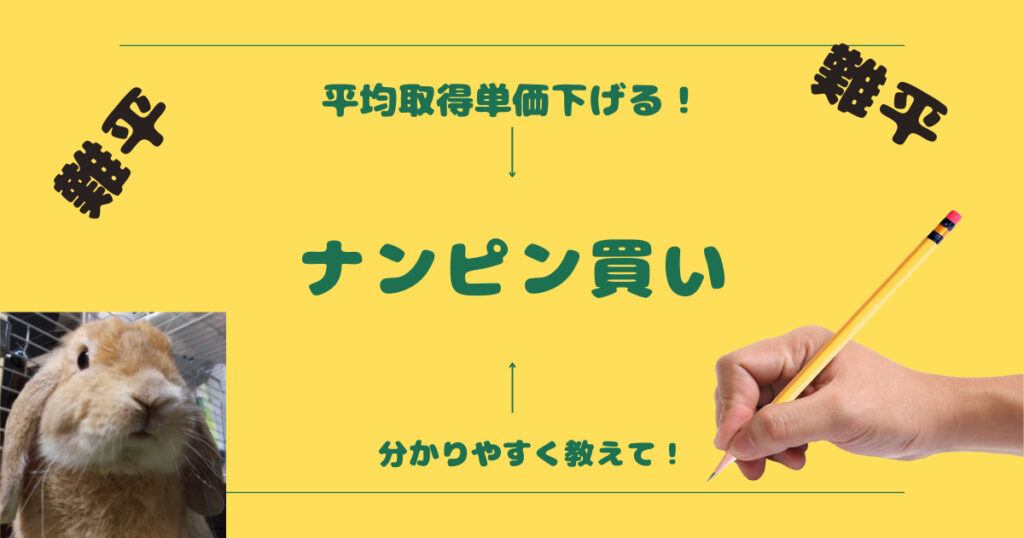

ナンピン買いだと⁉それはどんなお買い物なんだ!と思う人が100人に1人ぐらいいるかもなので、
徒然なるままに書き散らしていきます。
ナンピン買いとは、『保有してる株の値が下がったときにさらに追加購入して平均取得単価を下げる』という株の買い方になります。どういうことかと言うと、
例えば、A株1000円を100株保有していたとします。忘れたころに株価みてみたら、な、なんとA株が500円に下がっていたと絶望します。今売却すると一株あたり500円の損失=5万円の損失なので、また上がるまで保有しとくことにしようと心に誓ったとします。
でも、1000円まで上がる感じが全くしないとか、もしくはいつかは1000円を超えそうやけどまだまだ時間がかかるなぁとか考えつつ、500円のときに追加で100株購入したとしましょう。
すると1000円で100株の保有分と500円で100株なので平均取得単価が変わり平均取得単価は一株あたり750円を200株保有となり、平均取得単価を下げることができました。
これをナンピン買いと言います。漢字では難平買いで、難(なん)を平(たいら)にするからと言われたり言われなかったり。
なので、メリットとしては平均取得単価を下げることができるので、今後上昇が見込まれる場合は損失を少なくできるし、750円を超える株価になった場合は利益となりしかも200株分なので大きな利益も見込めます。
もちろんその反動としてナンピン買いをしたはいいものの、さらに株価が下がるようなことがあれば損失がめちゃ増えるということになります。
なので、何でもかんでもナンピン買いすればいいというわけではなく、見極めが大事になります。
それとおもち的には小刻みにナンピン買いするのは経験上おすすめしないです。
例えば、1000円の時に100株、900円の時に100株追加、800円の時に100株追加と繰り返し追加して500円まで株価が下がり気づけば、500円の時にナンピンにつぐナンピンで600株保有していたとします。平均取得単価は、
(1000円+900円+800円+700円+600円+500円)÷6=750円となり株価500円に対して、平均取得単価は750円で600株保有となります。この地点で一株あたり250円の含み損なので、250円×600株=15万円のマイナスです。
自分なりに今後株価の上昇が見込める材料などがあり、メンタル的に耐えれる人はいいかもですが、少し株価が変動するだけで、大きく金額が動くのは結構メンタルに響くことがあります。なので、ナンピン買いは細かく購入するよりも、
1000円で100株保有が500円になったから100株追加、これなら平均取得単価は750円と同じでも保有株数は200株なので、気持ち的には損切するにも気持ち楽だし、今後あがれば利益も良い感じになることが多い気がします。
と、平均取得単価を下げる方法もあるんだぞ!ということを説明しました。

以上今回は、平均取得単価について説明しました。
現物取引での同じ銘柄を当日に売買する場合の注意や、
平均取得単価を下げて利益狙いや損失を抑えるナンピン買いなどについて
説明しました。分かりやすいと思ってもらえたら嬉しく思いますが、
分かりにくいと思った方はもう一度読み返して、それでも分からなかった場合はすいません。
ここまで読んでくれた方に感謝です。感謝のナンピン買い3回です!では☆

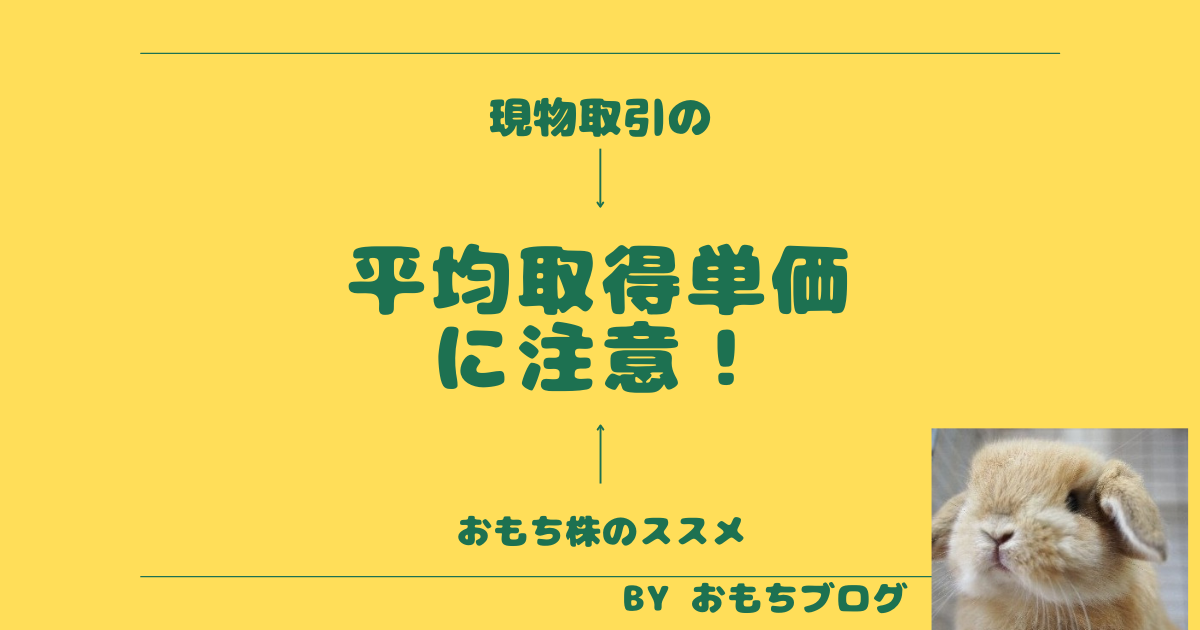

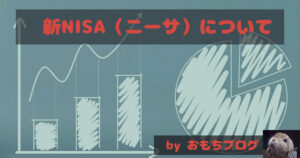
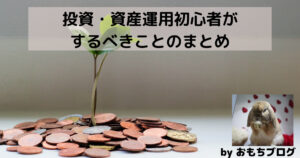
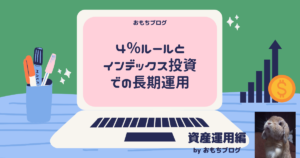

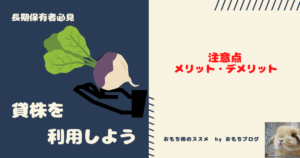
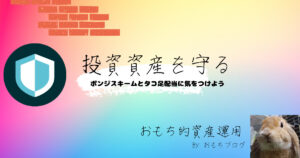

コメント